
公務員ラボへようこそ。




この記事では、公務員試験に複数合格した私が、面接対策に必要なことを「全て」教えます。
- 膨大な数の想定問答
- 面接練習による徹底的な「場慣れ」
- 最低限の自己分析
これだけです。
おそらく誰もがやることですが、量も質も不十分である場合が多いんです。
ちなみに逆に言えば、これさえ徹底できれば、これ以外は時間をあまりかけなくても良いということです。
目次
想定問答を徹底的に行う【目安は50個】

まず重要なことは、「想定問答をたくさん作り、ひたすらその回答の練習をする」ことです。
目安としては、最低50個はあると安心ですね。
「まずは自己分析じゃないの?」と思う方もいるでしょう。
想定問答を作る前の自己分析に関しては、最低限の対策にしておきましょう。
例えば、以下の「グッドポイント診断」で強みを把握しておくのがおすすめです。
その後は、もちろん志望動機・やりたい仕事などの基礎を決める必要はありますが、あとは上記のグッドポイント診断で強みを把握したら、いきなり想定問答から入っても構いません。
想定問答をたくさん行う意味
そもそも、なぜ想定問答が重要なんでしょうか。
それは、「コミュニケーション能力が高い風」に見せるためです。

「スラスラ喋る必要はない。自分の言葉で話せれば人柄が伝わるから大丈夫」みたいな言葉、聞いたことありますか?
ぶっちゃけ、面接官の心証はスラスラ喋る人のほうが良いですよ。
そもそも30分やそこらの面接で、受験生の人柄なんて見抜けるはずがないんです。受験生側も人柄を偽装している人が少なくないですから。
もちろん「覚えた文章を読んでる感」を出すのはNG
これは当然と言えば当然なのですが、出来ていない人は意外といるんです。
私も集団面接などで「原稿を読むような喋り方」をしている人を見かけました。
人事側も、「想定問答を覚えてくる受験生もいるのは仕方ない」という暗黙の了解はありますし、「覚えてきているのがバレないように喋る」ところまでできていれば問題ないんです。
ただ、やはり覚えてきた文章だと露骨にわかる話し方は、かなり印象が悪いです。
なので、想定問答を作るだけでなく、話し方まで徹底しましょう。
やり方は簡単です。
- 自分が話しているところを録音して聞きながら、気になることろを改善していくだけです。
独学の人でもできますね?
本番で想定していなかった質問をされたら?
「想定問答を暗記するだけでは、予想外の質問をされたときに対応できない」と思う方もいるでしょう。
正直、50個以上想定問答を作っておけば、その50個に全く関連していない質問をされることは少ないです。
関連している質問であれば、少し内容をアレンジするだけで答えられるでしょう。
では、その50個とは関係ない内容を聞かれたらどうするか。
- それでも、きっとその50個の中にヒントがあります。「少し考える時間をいただいてもよろしいでしょうか」と言って、よく考えましょう。
正直、この「予想外の質問」に対する答えというのは、どんな面接対策をしていようが難しいです。
自己分析に力を入れていたり、面接対策の本を10冊読んでたとしても、中々答えられないでしょう。
そして、面接官もそれを分かったうえで質問をしてます。
その時間で、想定問答の中からなんとか糸口を見つけましょう。
1から回答を作るのは土壇場では難しいですが、想定問答という「より所」があるだけで、かなり楽になります。
割と変わった質問ですね。もちろん想定問答にはありませんでした。
私は、準備していた想定問答の「自分の長所」を応用して、「情熱の赤と冷静さの青をあわせ持った紫」と答えました。
正解はないですし、これはほんの一例です。
皆さんも、なんとか想定問答と結び付けて答えましょう。
ちなみに、民間であれば上記の質問よりも更にぶっとんだ質問もとんできますが、公務員試験ではこれくらいがマックスだと思っていいと思います。
あとは面接練習による「面接慣れ」がとにかく重要!

想定問答を50個以上作り、その回答について話す練習をしたら、あとはシンプルです。
面接練習をひたすら行いましょう。
面接練習の数=合格可能性 です。
これはあながち間違っていないと思います。一切誇張ナシです。
面接練習をそんなにやる意味は?
面接練習を繰り返し行うことによるメリットは以下の3点です。
- 想定問答の内容を改善
面接練習をひたすら繰り返せば、一通り想定問答で準備した内容は聞かれるでしょう。
自分では納得のいく想定問答であっても、繰り返し面接練習を行い、第三者目線での意見を積極的に取り入れることで、よりよい回答が作れるはずです。
- 好印象な話し方が身につく
話し方に関しては、自分で録音して聞くだけでも、そこそこ身につくでしょう。
ただ、本番の面接官はプロです。少し取り繕うだけでは、覚えた文章をそのまま読んでいることを見抜かれるでしょう。
なので、第三者の目線で何度も見てもらい、改善していきましょう。あなたから面接練習してくれる相手に対し、「話すスピードや抑揚、声の大きさはどうだったか」ということを毎回確認するといいです。
- 究極の面接慣れ
一番大きなメリットです。正直、これさえできてれば面接は怖くありません。
変わった質問がとんできても冷静に考える余裕が生まれますし、1日に何度も面接が行われる試験でもスタミナ切れを起こす心配はありません。
単なる面接官との会話だと思えるようになるまでやれば、合格は一気に近づきますよ。
以上が面接練習を繰り返すことによるメリットです。
では、具体的にどのように面接練習をすればいいのでしょうか。
面接練習をするに当たって、意識すべきポイントを次の項目で解説していきます。
面接練習をするにあたって気を付けるべきこと
- ほぼ緊張しなくなるまで面接練習を繰り返そう
面接練習って、3.4回やれば、「そこそこ面接ができる」くらいにはなるんです。なので、そこでやめてしまう人が多い。
そのまま続ければ他の受験生に差をつけられるのに、もったいないです。
本番では練習の5倍は緊張します。
「練習では殆ど緊張しない」という状態までやっておくことで、本番は適度な緊張感で臨むことができるはずですよ。
- 色んな相手に面接練習をしてもらおう
とはいえ、ずっと同じ相手に面接官をやってもらっていても、数回で緊張感はなくなってしまうでしょう。指摘されるポイントも毎回似たような内容になってしまいます。
そこで、別の人に面接官をやってもらいましょう。
これだけでも緊張感は出ますし、新たな視点からの意見をもらうことで、更に改良していくことができるはずです。
- 面接は録音して、自分で聞いてみよう
もちろん第三者目線での意見も重要ですが、自分で意識しているポイントが思い通りできているかを自分で確認してみることも必要です。
自分の面接を聞くのって恥ずかしくて抵抗がありますが、定期的に聞いてみてください。
独学の人はどうすればいいの?
独学の人は、面接練習する場がないですよね。

私は予備校に通っていましたが、特に予備校に通っていない方は色んな環境で面接をした方が良いのでおすすめです。
あとは、大学生の方は大学でも面接練習をやってくれるので、そちらも試してみるといいでしょう。
私自身も、スケジュール次第ではお受けしています。
公務員試験の面接対策で自己分析をしていない人は最低限しておこう
「自己分析はした方が良いけど、比較的重要ではない」というのが私の意見です。
重要でないということはないですが、「ある程度重要な地位を占めているが、想定問答や模擬面接と比べると重要性は落ちる」というのが正しいです。
理由は「自己分析ばかりしたところで、面接の質問に答えられるようにならないから」です。
もちろん、自分の長所を知ることや学生時代一番頑張ったことを掘り下げることは必要ですよ。
そんな公務員試験の最低限の自己分析には、グッドポイント診断がおすすめです。
8568通りのパターンから、客観的で正確な長所・強みを分析してくれるので、こういった数ある自己分析ツールの中でもかなり正確な結果が出る印象です。
以下で簡単なやり方を解説しているので、よかったら見てみてください。
公務員試験の面接対策まとめ
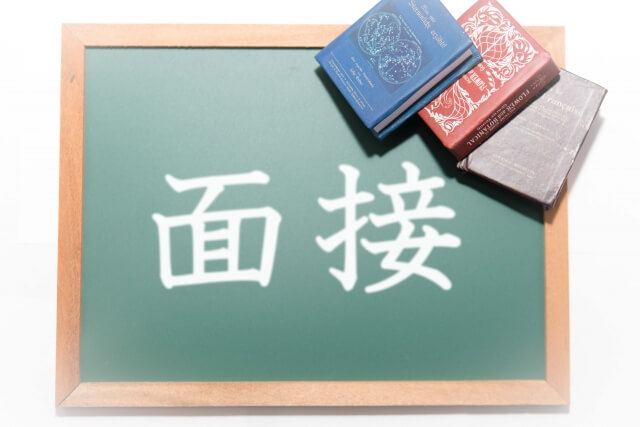
- 公務員試験の面接対策では、想定問答を50個以上作ろう!
- 面接練習は、ほぼ緊張しなくなるまで繰り返そう!
- 自己分析は相対的には重要度低めなので、想定問答と面接練習を徹底的に行おう!
今回は、私自身の受験生時代の経験と、人事の話を聞いて思ったことをベースに、公務員試験全般の面接対策を書いてみました。
この記事に加え、各々の第一志望の受験先の面接対策の記事(鋭意製作中)を読んでもらえれば、あとは実践するだけで合格まで一直線です。
「想定問答」と「面接練習」という誰もが行っているであろう2つの柱。
そこのみに注力して面接対策を行うことが、公務員試験の面接においては最も効率的です。
ぜひこの記事を参考に面接対策をして、合格をつかみ取ってください!
この記事が、公務員試験の面接対策で悩む皆様のお役に立てれば幸いです。














