
公務員ラボへようこそ。




市役所B日程・C日程・D日程の公務員試験は2018年度から新教養試験に変わり、ライト・ロジカル・スタンダードがメインの公務員試験となりました。
この記事では、元公務員で現役講師の私が、ボーダーや合格ライン、合格に必要な対策を「全て」書きます。
この記事を読んで実践すれば、間違いなく合格に一歩近づくと思うので、是非最後までお付き合いくださいね。
ちなみに、ライト・ロジカル・スタンダードの新教養試験が実施されるのは、B日程・C日程・D日程の市役所が中心となります。
A日程市役所は、地方上級の全国型と同じ問題が出ることが多いので、A日程を受験する方は以下の記事を読んでくださいね。
目次
新教養試験の出題科目・特徴【Light,Logical,Standard】

まずは、新教養試験の出題科目から見ていきましょう。
新教養試験は、スタンダード・ライト・ロジカルの3種類で、さらに細かくいうと以下の5つの試験に分かれています。
- StandardⅠ
- StandardⅡ
- LogicalⅠ
- LogicalⅡ
- Light
Standard・LogicalのⅠとⅡの違いは、難易度です。
StandardもLogicalもⅠの方が難しくなってはいますが、出題傾向自体にはほとんど差はありません。
では、それぞれの出題内容を紹介していきます。
なお、全タイプ共通で「古文、文学・芸術」の出題はありません。
Standard-Ⅰ・Ⅱ〈標準タイプ〉
Standardタイプの特徴は以下の通りです。
- 従来の教養試験に近い出題傾向
- 知能分野20問・知識分野20問の計40問
- 五肢択一で、制限時間は120分
- 時事の出題数が増え、ICT、環境問題、社会保障などが出題されるようになる
- 日本史・世界史・地理の出題数は1題ずつ=人文科学の出題は少ない
以上がStandardタイプの特徴になります。
ちなみに公務員試験において、「知能分野・知識分野」とは以下の科目を指します。
- 知能分野:数的処理・文章理解
- 知識分野:人文科学、社会科学、自然科学、時事
スタンダードの対策は後述しますが、基本的には従来の公務員試験に近いですね。
Logical-Ⅰ・Ⅱ〈知能重視タイプ〉
Logicalタイプの特徴は以下の通りです。
- 知能分野27問・知識分野13問の計40問
- 五肢択一で、制限時間は120分
- 自然科学の出題がない
- 時事の出題数が増え、ICT、環境問題、社会保障などが出題されるようになる
- 約8割の問題は、Standardと同じ問題が出題
Standardよりも知能分野を重視し、知識分野の出題を減らしたのがLogicalタイプですね。
知識分野の出題を減らしたとはいえ、従来の教養試験よりは時事を重視するようです。

自然科学が出題されない分、ロジカルの勉強すべき科目は少なくなっています。
ロジカル7も詳しい対策は後述します。
Light〈基礎力タイプ〉
Lightタイプの特徴は以下の通りです。
- 社会への関心と理解:24問、言語的な能力:18題、論理的思考力:18題
- 合計60問の四肢択一で、制限時間120分
- 難易度はStandardⅡやLogicalⅡより更に易しく、公務員試験対策をしてない民間志望者も受けやすい
- 地方自治に関する問題や、漢字の読み書きの出題がある
- 人文科学・自然科学の出題はない
ライトの難易度はかなり低めで、傾向的にはSPIの易しいバージョンと思ってくれればOKです。
公務員試験のSPIについて、気になる方は以下の記事を読んでみてください。
ちなみに、StandardとLogicalは共通の問題が多かったですが、Lightは全て独自の問題です。
【市役所】新教養試験のボーダー・合格ラインは?
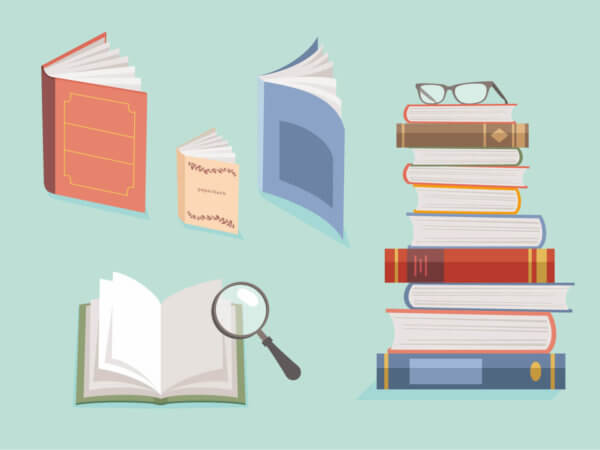
では、次に「Standard・Logical・Light」それぞれの公務員試験のボーダーや合格ラインを紹介していきたいと思います。
自信の受験先のボーダー・合格ラインをしっかり確認したうえで、効率的に対策していきましょう。
Standardタイプの難易度・ボーダー・合格ライン
問題自体の難易度は以下の通りです。
- Standard-Ⅰ:普通(≒都庁の教養試験)
- Standard-Ⅱ:易しい(≒SPI)
「Standard-Ⅰが従来の教養1と同じ、Standard-Ⅱが教養2.3と同じ難易度」と公表されているので、概ね間違いないでしょう。
そしてこの難易度を踏まえて考えると、スタンダードの大体のボーダーが予想できます。
- Standard-Ⅰ:5割~5.5割
- Standard-Ⅱ(大卒程度):5.5割~6割
- Standard-Ⅱ(高卒程度):5割~5.5割
あくまで予想ですが、Standardタイプの自治体を受ける方は、この合格ラインを意識してスタンダード対策をするようにしましょう。
Logicalタイプの難易度・ボーダー・合格ライン
Logicalに関して、問題自体の難易度は以下の通りです。
- Logical-Ⅰ:やや易しい(≒特別区の教養試験)
- Logical-Ⅱ:易しい(≒SPI)
「Logical-Ⅰが教養1よりやや易しく、Standard-Ⅱが教養2.3と同じ難易度」ということなので、概ね間違いないでしょう。
そしてこの難易度を踏まえて考えると、ロジカルの大体のボーダーが予想できます。
- Logical-Ⅰ:約5.5割
- Logical(大卒程度):5.5割~6割
- Logical(高卒程度):5割~5.5割
Logicalタイプの自治体を受ける方は、この合格ラインを意識してロジカル対策をするようにしましょう。
Lightタイプの難易度・ボーダー・合格ライン(例題あり)
Lightタイプは、他の2つとは異なる、全く新しいタイプの試験なので、難易度やボーダーの予想が難しくなっています。
そこで、Lightタイプのみ、試験を作成している団体が例題を公表しています。
この例題から、問題自体の難易度は明らかですね。
- Lightの難易度:非常に易しい
公務員試験の中ではライトがかなり易しめの位置にきます。
そしてこの難易度を踏まえ、大体のボーダーを予想します。
- Lightのボーダー:約6.5割
問題自体が易しい分、ライトでは当然ボーダーは高めになります。
Lightタイプの自治体を受ける方は、この合格ラインを意識してライト対策をするようにしましょう。
新教養試験対策の問題集・勉強法【ライト・ロジカル・スタンダード】

それでは、最後に新教養試験おすすめの参考書と勉強法を紹介します。
【Standard・Logical・Light】どの自治体を受けるかで対策や使用すべき問題集は異なり、対策を間違えると得点が伸び悩んでしまいます。
おすすめの対策を解説していくので、是非実践してみてくださいね!
Standardタイプの問題集と対策
Standardタイプは、以前の教養試験に近い試験になります。
なので、注意すべき点はありますが、概ね教養試験と同じ勉強法を実践すればOKです。
以下の記事で、教養試験の効率的な勉強法を解説しているので、気になる科目だけでも参考にしてください。
基本的にはスタンダードも以上の勉強方法でOKです。
ただ、Standardタイプの勉強では以下の点に注意してください。
- 時事・社会科学の勉強により力を入れる
- 出題数の少ない人文科学は、最低限の勉強で攻略
- 古文や文学・芸術は出題されないので、勉強しない
似ているとはいえ、教養試験と全く同じ勉強では効率が下がってしまうので、以上のことには注意するようにしてください。
また、上記の教養試験の記事からも分かる通り、問題集はほとんどの科目で「スー過去」をおすすめしてます。
Standardを受けるのであれば、プラスαの問題集として「市役所上・中級試験過去問500」をおすすめします。
スー過去の後に過去問500をやることで、市役所試験に特化した勉強ができ、スタンダードでの得点がかなり安定するようになるので、是非試してみてください。
ということで、Standardは「スー過去メインで学習→過去問500」の流れがおすすめです!
Logicalタイプの問題集と対策
Logicalタイプに関しては、8割がStandardと同じ出題ということで、基本的にはStandardと同じ対策でOKです。
まず、上記でも紹介した教養試験対策の記事を参考に、スー過去メインで勉強しましょう。
この時にロジカル対策で気を付けるべき点は以下の通りです。
- 時事・数的処理の勉強にとにかく力を入れる
- 社会科学・人文科学は最低限の勉強で攻略
- 古文や文学・芸術に加えて自然科学も、基本は出題されないので勉強しない
次にStandardであれば「過去問500」をやるところですが、Logicalでは「過去問500」は不要です。
「過去問500」も十分Logical対策になりますが、もっと優れた問題集があるんですよね。
なぜなら、「市役所新教養試験 Light&Logical 早わかり問題集」という新教養試験に特化した唯一の問題集が出版されたからです。
この問題集を出版している「実務教育出版」は、公務員試験で最も有名な過去問集「スーパー過去問ゼミ」などの出版社なので、間違いなく信用できます。
ということで、Logicalは「スー過去メインで学習→早わかり問題集」の流れが絶対におすすめです。
Lightタイプの問題集と対策
Lightタイプに関しても、「市役所新教養試験 Light&Logical 早わかり問題集」がおすすめです。
ただ、「早わかり問題集」はLogicalだけでなくLight対策の部分も基礎を抑えるという意味では十分優秀なので、まずはこれをやってライトの基礎を固めまししょう。

2冊目としては、「公務員教科書 1か月完成 動画とアプリで学ぶ 市役所新方式試験 SPI・SCOA・Light・社会人基礎」という参考書が圧倒的におすすめです。
現時点ではLight対策の中で最も新しい問題集で、2023年の5月に初版の参考書なのでまだそれほど使っている受験生は多くないですが、新しい参考書というのは強みになります。
最新の傾向を反映しており、とにかく質の高い参考書という印象です。
問題ごとにどの形式で出やすいかが示されており、非常に効率的に学習できるかと思います。
ただ、見た目もコンパクトですし、これだけ多くの試験種に対応しているとLightの問題に限定すると「問題数が足りない」と思われがちです。
内容もわかりやすい上に、問題数が少ないLightの参考書・問題集の中では、問題演習も多めにこなすことができるので、個人的にはおすすめできます。
「早わかり問題集→「公務員教科書 1か月完成 動画と~」」の流れでやっておけばLight対策は万全でしょう。
(2024/07/26 21:14:07時点 楽天市場調べ-詳細)
新教養試験対策の問題集・合格ライン・ボーダーまとめ
- Standardの対策は「スー過去→過去問500」
- Logicalの対策は「スー過去→早わかり問題集」
- Lightの対策は「早わかり問題集→「公務員教科書 1か月完成 動画とアプリで学ぶ 市役所新方式試験 SPI・SCOA・Light・社会人基礎」」
- 新教養試験は【Standard・Logical・Light】それぞれの合格ライン・ボーダーを踏まえたうえで対策をしよう!
まだ始まって数年の新教養試験ですが、逆に「それをアドバンテージにすることができる」というのを最後に皆さんに伝えたいです。
この記事には、新教養試験について、合格するために必要な知識・効率的な勉強法が「全て」詰まってます。
つまり、あなたはこの記事の内容をしっかり実践すれば「合格までの最短距離」を行くことができます。
新教養試験は情報が少ない分、遠回りする人が多い中で、これは大きなアドバンテージになります。
なので、この状況をチャンスだと思ってください。
この記事の内容を実践し、合格までの最短距離を走り、周りに差をつけていきましょう!
この記事が、新教養試験対策(ライト・ロジカル・スタンダード)で悩む皆様のお役に立てれば幸いです。
以下の参考書・問題集は新教養試験対策に特におすすめなので、是非試してみてください。
このサイトでは他にも、公務員試験で複数上位合格した現役講師の私が、筆記・面接・論文について解説しています。
公務員試験に必要な情報は全てここに詰まってるので、是非見ていってください。




















