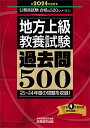公務員ラボへようこそ。




確実にあなたの合格の助けになると思うので、是非最後までご覧下さい。
この記事では、筆記試験対策に絞って紹介します。
面接対策は筆記試験が終わってからでもOKですが、筆記試験前に行っておく面接対策としては、以下の方法で自身の強みを把握しておくことがおすすめです。
目次
神奈川県庁のボーダー・倍率・難易度・学歴

さて、まず神奈川県庁採用試験のボーダーや倍率、難易度を知っておきましょう。
受験先の特徴を知っておくのは大事ですからね。
神奈川県庁の倍率は高め
- 一般行政A
| 受験者数 | 一次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
| 978 | 541 | 383 | 164 | 4.6 |
※辞退者を含めた実質倍率は、4.2倍です。
他の都道府県庁と比べると、倍率は少し高めと言えるでしょう。

1次試験の倍率は1.8倍、2次試験は2.3倍です。
筆記試験の倍率は比較的低く、面接の倍率も高くないことがわかりますね。
神奈川県庁の筆記試験のボーダーは〇割!
神奈川県庁では正式なボーダーは公表されていません。
基本的に、地方上級試験のボーダーは基本的に5.5割~6割になっています。
そこで、神奈川県庁の倍率や受験生に聞いた話から判断すると、神奈川県庁のボーダーは5.5割前後だと言えます。
年によってはこの範囲で変動はしますが、ボーダーが5割より低くなったり、6割より高くなることは基本的にないでしょう。
神奈川県庁の難易度は?
神奈川県庁の難易度は、普通程度です。
後述しますが、筆記試験は倍率が2倍を切っているうえに、専門試験が独自型をとっており、80問の中から選択できるので得点しやすい形になっています。
面接試験に関しては倍率が低くも高くもないですね。
なので、受験生のレベルが少し高くなることを加味し、難易度は普通程度としました。
神奈川県庁入庁者の学歴
神奈川県庁入庁者には、どれくらいの学歴の方が多いのでしょうか。
神奈川県庁には何人か知り合いがいるので、聞いてみました。
以下の学歴の方が多いようです。
- 横浜国立大学
- 横浜市立大学
- MARCH
- 日東駒専
また、偏差値で言うと日東駒専よりも下がる大学や、早慶もいるということなので、幅広く採用しており、学歴は重視してないようです。
神奈川県庁合格に必要な勉強時間は?
神奈川県庁合格に必要な勉強時間は、1300時間前後が目安です。
基本的に公務員試験の勉強時間は1000時間~とされています。
神奈川県庁では教養・専門・論文と3つの勉強をしなければいけないうえ、やはり首都圏の県庁なので、これくらいの勉強時間が必要にはなってきます。

神奈川県庁の出題科目【教養・専門試験】

基本的に地方上級は全国型・関東型・中部北陸型の3つに分かれていますが、神奈川県庁の試験は以下の通りです。
- 教養試験は関東型
- 専門試験は独自型
「独自型ってなに?」と思われる方もいるかもしれませんので、ここで出題科目を載せておきますね。
教養試験の出題科目
関東型は選択回答ですが、赤字の部分は必須回答になっています。
| 科目 | 出題数 | 重要度 | 難易度 | 内訳 |
| 文章理解 | 9 | 〇 | 普通 | 現代文:3 英語:5 古文:1 |
| 数的処理 | 12 | 〇 | やや難 | 数的:6 判断:5 資料:1 |
| 人文科学 | 9 | ◎ | 普通 | 日本史:3 世界史:3 地理:2 文学・芸術:1 |
| 社会科学 | 13 | ◎ | やや難 | 政治:1 法律:3 経済:3 社会:6 |
| 自然科学 | 7 | △ | やや易 | 化学:2 物理:1 生物:2 地学:1 数学:1 |
| 合計 | 40/50問を選択回答 | ー | 普通 |
ー |
専門試験の出題科目
専門試験は独自型ということで、かなり選択の幅が広い問題選択式になっています。
| 科目 | 出題数 | 重要度 | 難易度 |
| 憲法 | 5 | ◎ | やや易 |
| 民法 | 7 | ◎ | やや難 |
| 行政法 | 6 | ◎ | 普通 |
| 経済学 | 15 | ◎ | やや難 |
| 経済政策 | 2 | 〇 | やや難 |
| 経済事情 | 1 | △ | やや難 |
| 経済史 | 1 | △ | 普通 |
| 財政学 | 2 | 〇 | やや難 |
| 政治学 | 2 | 〇 | 普通 |
| 行政学 | 2 | 〇 | やや易 |
| 経営学 | 2 | 〇 | やや易 |
| 国際関係 | 4 | △ | 難 |
| 社会政策 | 2 | 〇 | 易 |
| 刑法 | 2 | × | やや易 |
| 労働法 | 2 | △ | 易 |
| 心理学 | 3 | × | |
| 教育学 | 3 | × | |
| 統計学 | 3 | × | |
| 数学 | 5 | × | |
| 物理 | 4 | × | |
| 情報工学 | 4 | × | |
| 合計 | 40/80問を選択回答 | ー | 普通 |
下の6科目は、大学で専攻していたなどの理由がない限り選択はおすすめできません。
神奈川県庁の筆記・面接の配点【リセット方式】
神奈川県庁は「筆記試験の結果を2次試験で考慮しない」リセット方式を採用しています。
択一試験の結果はボーダーギリギリでも、9割とっていても2次試験では横並びになるわけです。
なので、最終合格の順位は面接と論文だけで決まるということですね。
ただ、「リセット方式だから筆記の勉強は最低限でいいや」と考える人はいませんよね?
神奈川県庁の筆記・面接の配点
続いて、受験先の配点も非常に重要なので、配点を把握してメリハリをつけて対策をするようにしましょうね。
神奈川県庁の配点は以下の通りです。
- 教養試験:100点
- 専門試験:100点
- 論文試験:50点
- グループワーク:50点
- 面接試験(1回目):50点
- 面接試験(2回目):400点
まあ実際はこの配点通りではなく、リセット方式なので教養と専門の得点はリセットされます。
配点は以下のように表した方がわかりやすいかもしれませんね。
1次試験の配点は教養:専門=1:1
2次試験の配点は論文:GW:面接1回目:面接2回目=1:1:1:4
神奈川県庁の筆記試験対策【教養・専門】
それでは、神奈川県庁の筆記試験対策に移ります。
教養・専門それぞれについて紹介してきますね。
神奈川県庁の教養試験対策
神奈川県庁は、関東型の試験に当たります。
そこで、以下の記事で神奈川県庁(関東型)に特化した勉強法を全て紹介しています。
上記の記事を参考に、神奈川県庁にターゲットを絞った勉強をしましょう。
多くの受験生は、神奈川県庁の対策に特化した勉強はしていません。
「公務員試験対策」という漠然としたくくりでしか勉強していないのです。
なので、志望度が高い試験に関しては、その受験先の特徴を把握し、それに応じた効率的な対策を行うことで確実に差をつけられます。
私が上位合格できた要因として「受験先特化の勉強法を考え、実践できたこと」はとても大きかったと思っています。
私自身はこの「受験席特化の勉強法」を考えるのに長い時間を費やしましたが、あなたはそこに時間をかける必要はありませんよ。
なので、あなたも上記の記事を読み、神奈川県庁の試験に特化した対策を行いましょう!
神奈川県庁の専門試験対策
専門試験も、意識すべき点は教養と同じです。
独自型とはいえ、地方上級の関東型と似たような出題数になっています。
なので、基本的には先ほど紹介した関東型の記事の専門試験対策を参考にしていただければOKです。
関東型とは出題数の違いはありますが、神奈川県庁では80問の出題なのに対し、関東型は50問なので、出題数が異なるのは当然です。
出題数ではなく「出題割合」で考えると、どの科目が重要かについては同じですし、実際に出題される問題の傾向もある程度似ています。
なので教養と同じように、しっかりと神奈川県庁に特化した対策をするようにしてくださいね。
唯一異なるのが、その「80問出題されるか、50問出題されるか」なので、おすすめ選択科目についてだけ解説しておきますね。
神奈川県庁の専門試験の選択科目
専門試験の選択科目については、以下の科目を選択するのがおすすめです。
合格者数名に選択科目を聞いた結果なので、信頼できる情報になっていると思いますよ。
- 憲法
- 民法
- 行政法
- 経済学
- 経済史
- 経済事情
- 財政学
- 政治学
- 行政学
- 社会学
- 経営学
- 社会政策
- 労働法
合格者数名に聞いたところ、以上の科目を選択していることが多かったです。
これで合計49問なので、その中から40問選択すると考えたら十分ですね。
これがおすすめというか、基本的にこれをベースに考えた方が良いです。
ちなみに、4問も出題されている国際関係ですが、学習範囲が膨大である上に出題難易度も高めなので、あまり選択する人は少ないようです。
神奈川県庁受験者が最優先でやっておくべき対策【特に直前期】
神奈川県庁は、経済学をはじめ、一部の科目で少し独特の癖があります。
そのため、地方上級の過去問は必ずやっておくべきです。
特におすすめなのは、やはりとても多くの受験生が使っている地方上級 過去問500です。
(2024/07/26 23:08:02時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/07/26 23:08:02時点 楽天市場調べ-詳細)
直前期は「過去問500」、時間のある方は「スーパー過去問ゼミ」
直前期には間違いなく「過去問500」で地方上級の過去問のみに絞った問題をやっておくべきです。

そこで、時間がある程度ある方には、全科目に共通して「スーパー過去問ゼミ」がおすすめです。
よって、
神奈川県庁の論文試験対策

神奈川県庁では、論文試験が実施されます。
配点は50点と決して高くはありませんが、しっかり勉強しておかなければ差がつく点数です。
神奈川県庁の論文試験の過去問
厚生労働省が実施した「平成 28 年国民生活基礎調査」によると、我が国の子どもの貧困率※は 13.9%(約7人に1人)となっており、先進国の中でも高い水準にある。特に子どもがいる現役世帯(世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世帯)のうち、大人が一人の世帯の貧困率は 50%を超えている。こうした状況の要因について考察し、それに対するあなたの考えを論じなさい。(H30過去問)
※子どもの貧困率:17 歳以下の子ども全体に占める、貧困線(等価可処分所得の中央値の半分の額)に満たない 17 歳以下の子どもの割合。
こちらの過去問は「子供の貧困」ということで、頻出テーマになりますね。
テーマの予想も可能な範囲だったでしょう。

神奈川県庁の論文試験の勉強法
そして、これはテクニック的なものになりますが、「減点を減らし、更に高得点を狙う」ために以下の内容を詰めておきましょう。
最後に、「予想外のテーマが出題されたときの対策」として、以下の記事を書きました。
神奈川県庁でも、過去に頻出テーマでない問題の出題はあるので、上記の方法は十分活きると思います。
そういった年は、そこそこの答案が書ければ十分上位に食い込めますよ。
ここまでの方法を全て実践すれば、正直怖いものはありません。

神奈川県庁の論文試験を受けるにあたって必読の計画とは?
「長期計画や総合計画に目を通しておくように」とはよく言いますが、正直目を通すだけでは論文でも面接でもとっさに使うことは絶対にできません。
頻出テーマだけで良いので、何かしら神奈川県が行っている取り組みや方針を「暗記」しておくようにしてください。
受験先の知識をアピールすることは、論文の加点要素として非常に大きいですからね。
おまけ:神奈川県庁の試験を受けるときの服装は?

最後に、神奈川県庁を受験する際の服装についてです。
- 筆記試験の服装→私服
- 面接・グループワークの服装→スーツ
これでOKです。
筆記試験では基本的にスーツを着る必要はありません。
理由は以下の記事で詳しく解説しています。
神奈川県庁は受験人数も多いので、筆記試験でいちいち把握なんてできないですしね。
ただ、神奈川県庁では試験種によっては面接でも「服装は自由。リラックスできる服装で」という指定がある場合があります。
仮に指定があった場合は、もちろんその通りにしましょう。
神奈川県庁の筆記試験・論文対策まとめ
- 神奈川県庁の難易度・ボーダー・倍率は高くも低くもない!
- 神奈川県庁の合格に必要な勉強時間は1300時間前後!
- 教養試験・専門試験対策はどちらも地方上級関東型に特化した勉強を心がけよう!
- 論文試験対策は、かながわグランドデザインの「プロジェクト編」を読んだうえで、更に予想外のテーマが出題されたときの対策も学んでおこう!
- 筆記前に面接対策に時間をかける必要はないが、自己分析だけでもやっておけるとベスト!
神奈川県庁は、首都圏の県庁ということもあり、倍率・難易度は低くありません。
ただこの記事でも書いた通り「神奈川県庁の試験に特化した対策」を意識できれば合格は決して難しくありません。
ボーダーは高くないですし、専門試験も得点しやすい試験方式ですからね。
特別区、国家一般に上位5%以内で合格した私が実践した方法なので、間違いない勉強法だと思いますよ。
あなたもこの記事を読み、「神奈川県庁の試験に特化した対策」を心がけて、合格までの最短距離を行ってください!
この記事が、神奈川県庁の筆記試験・論文対策で悩む皆様のお役に立てれば幸いです。