
公務員ラボへようこそ。




- 専門記述がある
- 択一でも記述でも労働法が重要
目次
労働基準監督官の出題科目【教養・専門択一・専門記述】

まず、労働基準監督官の出題数と難易度を表にまとめました。
労基に関しては、試験の特徴を知っておくことはとても重要ですからね。
また、下の表の「重要度」と「難易度」という指標が少しあいまいなので、説明しておきます。
- 重要度は、労基の選択科目としてのおススメ度です。
- 難易度「科目としての勉強難易度」というより、「労基で出題される問題の難易度」のことです。
(例:民法は勉強するのは大変な科目だが、労基ではあまり難しい問題は出ないので難易度は普通など)
ちなみに、難易度や重要度の算出には、以下の事項を参考にしています。
- 私の受験生時代の経験
- チューターをしていた頃の予備校生の意見
- 某予備校が毎年出している財務の試験データ
間違いなく信頼のおけるデータになっていると思いますので、是非参考にしてくださいね。
教養試験の出題科目と難易度
| 科目 | 出題数 | 重要度 | 難易度 | 内訳 |
| 文章理解 | 11 | ◎ | やや難 | 現代文:6 英語:5 |
| 数的処理 | 16 | ◎ | やや難 | 数的:5 判断:8 資料:3 |
| 人文科学 | 4 | △ | やや易 | 日本史:1 世界史:1 地理:1 思想:1 |
| 社会科学 | 3 | 〇 | 普通 | 政治:1 経済:1 社会:1 |
| 自然科学 | 3 | △ | やや易 | 化学:1 物理:1 生物:1 |
| 時事 | 3 | 〇 | 普通 | ー |
| 合計 | 40 (必須回答) |
ー | 普通 |
ー |
労基の教養試験は、国税・財務と同じ問題が出題されます。
別名「基礎能力試験」ですね。
特徴としては、以下の通りです。
- 専門に傾斜がかかるので、教養の重要性は少し下がる
- 現代文・資料解釈・判断推理の出題が多い
専門択一の出題科目と難易度
赤字は必須科目となっており、その他黒字の科目の中から2科目を選択します。
| 科目 | 出題数 | 重要度 | 難易度 |
| 労働法 | 7 | ◎ | 普通 |
| 労働事情 | 5 | ◎ | やや易 |
| 憲法 | 4 | 〇 | やや易 |
| 行政法 | 4 | 〇 | 普通 |
| 民法 | 5 | 〇 | やや難 |
| 刑法 | 3 | △ | やや難 |
| 経済学 | 13 | ◎ | 普通 |
| 労働経済・社会保障 | 5 | 〇 | やや易 |
| 社会学 | 2 | △ | 普通 |
| 合計 | 40/48(一部選択回答) | ー | 普通 |
労働基準監督官の専門試験は、かなり独特の試験と言えます。
特徴は以下の通りです。
- 他の試験と比べて「憲法」や「民法」の出題が少ない
- マイナー科目「労働法」や「労働事情」が重要な科目となる
- 選択科目だが「経済学」の出題数が多い
具体的な対策は後述しますが、専門択一は労基で最も重要なので、重点的に対策しましょう。
専門記述の出題科目と難易度
| 科目 | 重要度 | 難易度 |
| 労働法 | ◎ | やや易~普通 |
| 労働事情 | ◎ | 普通 |
労基の専門記述は、2科目の必須回答になります。
いずれも他の試験で記述の出題がある科目ではないので、併願で勉強するのは難しい科目と言えます。
では、基本情報を把握したところで、勉強法を紹介していきます。
労働基準監督官の教養試験の勉強法・参考書

労働基準監督官の教養試験は、国税や財務と全く同じ問題が出ます。
なので、教養の勉強法については以下の記事を参考にしてください。
ちなみに配点比率は国税と同じで、教養:専門択一:専門記述=2:3:2です。
見ての通り、専門択一が最も重要です。

なので、教養・専門記述は最低限の勉強で済ませ、専門択一で確実に得点できるようにしましょう。
労働基準監督官の専門択一の勉強法・参考書
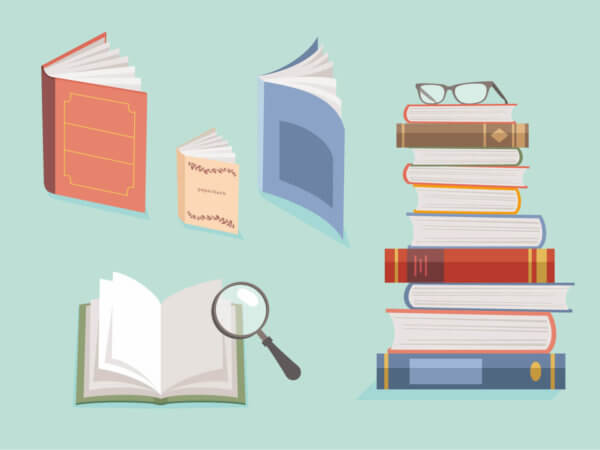
効率的に労基の合格を目指すのであれば、専門択一は最も重要になります。
そこで、まず専門試験の各科目の勉強法を以下で紹介しています。
労基専用の対策ではありませんが、勉強法自体は変わらないので、まずはそちらを読んでみてください。
次に、労基専用の対策として、注意が必要な科目のみを抜粋して紹介していきます。
経済学
労基では、経済学の出題数が13問と非常に多くなっています。
13問も出題されると、得意不得意でかなり差が出てしまいますからね。
具体的な勉強法は以下の記事で解説しています。
苦手な方でも確実に得点を伸ばせる勉強法だと自信を持って言えるので、是非参考にしてみてくださいね。
労働法【最重要科目】
労働法の勉強法は、以下の記事で解説しています。
簡単に言えば、労基受験者は「スーパー過去問ゼミ」を使うのが一番です。
労働法の「スー過去」は問題の選定や解説が素晴らしく、間違いなくベストな参考書です。
出題数が7問と多くなっているうえ、専門記述にも活きるので、しっかり対策しておきましょう。
特に導入本などはいらないので、正文化でひたすら過去問演習をするのが合格への近道です。
労働事情、労働経済・社会保障
「労働事情」「労働経済・社会保障」は専用の参考書がないのですが、「社会政策」という科目をやっておけばどちらも対策できます。
それに、出題される問題パターンは限定されており、基本的な問題しか出題されないので、基礎レベルだけ対策しておけば十分です。
まずは、「本試験過去問題集 労働基準監督官A」の該当部分を解いておきましょう。
あとは「公務員Vテキスト 社会政策」を参照し、重要部分のみでいいので知識を補強しておきましょう。
これだけやっておけば十分対応できるはずです。
労働基準監督官の専門記述の勉強法・参考書

労基の専門記述は、2科目ともマイナー科目が出題されます。
そのため、勉強法もあまり確立されておらず、参考書も専用のものはありません。
ここでは、私が労基の専門記述で使えそうな参考書をいくつも読んだ中で、ベストだと思ったものを紹介します。
できれば予備校に通うのがベスト
前提として、こういった専門の参考書がない科目の勉強をする場合は、予備校に通うのがベストです。
予備校に通えば、専用の参考書がありますし、わかりやすい講義も受けられます。
ただ、もちろん金銭的に通うのが厳しいという人はいますよね。
そういった方向けに、「予備校生と独学受験生の差」をできるだけ小さくするような勉強法・参考書を紹介していきます。
独学受験生向けの勉強法・参考書
まず参考書に関して、専用のものはありませんが、以下で代用することができます。
- 労働法→「プレップ労働法」
- 労働事情→「公務員Vテキスト 社会政策」
専門記述用に出版されたものではありませんが、労基の記述で出題される重要範囲は十分網羅されているため、どちらもおススメです。
勉強法は2科目とも共通です。
勉強法としては、何度も通読した後、過去問を見ながら上記の参考書で出題されそうな論点を選び、いくつか練習として記述の答案を作ってみましょう。
もちろんこれは単なる「書く練習」なので、そこで選んだテーマが出題されなくても問題ありません。
むしろ、「何度も通読すること」の方が重要です。
労基の記述で求められるハードルは高くないので、答案としては未熟でも、要点さえ書ければ問題はありません。
できれば4.5回くらいは読んでおいてください。
労働基準監督官の対策まとめ
教養・専門択一・専門記述とそれぞれ紹介してきました。
何度も言うようですが、やはり労基に合格するために重要なのは専門択一です。
「専門択一の勉強を重点的に行い、教養と専門記述は最低限の得点を確実にとれるようにする」のが合格への一番の近道です。
専門試験の各科目の勉強法を最後にもう一度貼っておくので、確実に差をつけられるようにしておいてくださいね。
この記事が、労働基準監督官の対策で悩む皆様のお役に立てれば幸いです。
この記事を読んでわからなかったこと、その他公務員試験に関して、公務員の仕事に関して、なんでも気軽に聞いてくださいね。
















